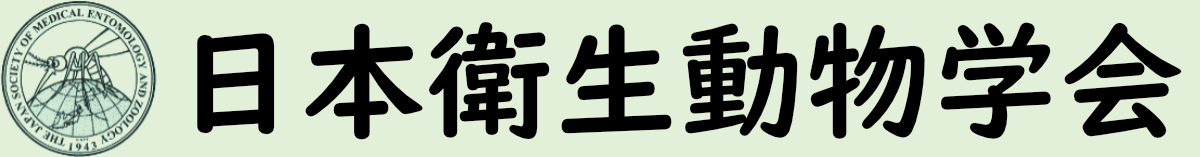平林公男(信州大学繊維学部)
日本衛生動物学会 第25期会長 (2024-)
2024年1月から2026年12月までの3年間、日本衛生動物学会第25期の会長を務めさせていただくことになりました信州大学の平林公男です。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。コロナ禍というこれまでに経験したことが無い状況の中で、有意義な学会活動とはなにかを突きつけられた数年間でありました。昨年春からようやく、コロナ禍前の日常生活が少しずつ取り戻され、学会での活動も多くの先生方のご努力で再開されました。編集委員の先生方のご努力で、会誌も年間4号発刊され、年大会や支部大会なども対面で実施されました。夏秋前会長をはじめとする前執行部の先生方や会員の皆様方のご協力の賜であると思っております。伝統ある本学会の益々の発展のために、尽力して参りたいと思いますので、どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
当学会では、会員数の減少や会員の高齢化に伴い、学会の行く末や経済状況は今後、けして明るいものではないと認識しております。若手会員の増加への取り組み、効率的な予算配分、事務手続きの簡素化・電子化、より魅力的な学会誌の発刊と本学会の広報など、一刻も早く対応を検討し、実施していかなくてはならない問題が山積みとなっております。本学会のもつ衛生動物に関する豊富で多様な会員の知的財産をいかに社会にアピールし、還元していくかが、今後、大変重要になってくるかと思っております。そのツールの一つとして、衛動誌の充実や本学会主催の各種セミナー、講演会、講座などの積極的な開催が考えられます。特に衛生動物に関する分類学的な研究の重要性は、今後、益々大きくなってくるものと予想され、本学会としても多くの会員のご協力を得ながら、体系的に本学会誌等を利用しながら整理をしていかなくてはならないと思っております。また。夏秋前会長からの引き継ぎ事項の一つとして、「衛生動物学・学術用語集(第2版)」編纂についても進めていかなくてはならないと思っております。
アフターコロナに向かう今、本学会においても「国際化」や「ジェンダーレス」などのキーワードが重要になってくるかと思います。「多くの多様な会員が、切磋琢磨する環境の中で、自由な発想で思うがままに研究活動を行うことが出来る」そんなオープンマインドな学会を創造していけると良いと思っております。科学に携わる人間のコミュニティーは、自らの科学的興味・関心、知見・知識、技術により、持続可能な社会の実現と人類の幸福のために貢献できると強く確信しております。どうぞ、会員の皆様方におかれましては、活発な研究活動を実施して頂き、その成果を本学会誌を通して積極的に公表して頂きたく存じます。ご協力の程、どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
(2024年4月)